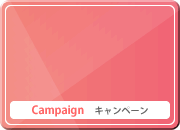読み手に響く文章は、どんな言葉から生まれるのか?
2025/03/13「賢そうな言葉をあまり知らないけれど、私にも書けますか?」

読み手の心に届く文章を書くために、
必要なモノって何ですか?
よくいただく質問です。
たくさんの言葉を知っていて使いこなせる力……
いわゆる「語い力」なのか。
作家やエッセイストのように
「行間を読ませる」表現力なのか。
はたまた、自分の仕事の専門性を
熱く語るこだわりなのか。
いろんな意見はありますし、
どれも間違いではありません。
言葉数はたくさん知っているほうが
絶対いいに決まっているし
表現力が豊かなほど、読んで面白い文章になるし
専門家として大切にしていることは
丁寧に伝えたほうがいい。
でも、その前に……私には、
もっと大切にしたいものがあるのですが、
それを改めて突き付けられた
SNSの投稿がありました。
このお話は、1年と少し前の取材が
スタート地点。
ちょっと時間をさかのぼらせてください。
取材をさせていただいたのは
「キャリアブレイク」という考え方を
広めていらっしゃる北野貴大さん。
キャリアをブレイクする……
すなわち「働く」ことを「休憩する」。
無職という行動を「働いていない」と
捉えるのではなく、
「自分への投資を通じて様々な体験を
している時間」と受け止める考え方。
欧州では、ひとつの文化として
受け入れられているものです。
北野さんのお話が楽しく、
また独創的で柔軟な発想が興味深くて
時間を忘れて聴き入った記憶があります。
その北野さんが、社会課題の解決を目指す
ソーシャルビジネス起業家を対象にした
ビジネスプランコンテストで、
今年2月、約400の応募の中から
準グランプリに選出されました。
その時の審査員の一人の方が記された
コメントに、心を持っていかれました。
全文は長いので、一部抜粋で
紹介させていただきます。
変化しないとダメだ、現状維持は後退と同じだ
と言われるように自分も思っているが、
「現状維持」と「変化する」の間の概念を教えてくれた。
それが、「立ち止まる」である。
変化しようという言葉はある人にとっては強すぎる。
歩み続けることをしようとしてより自分を追い込んでしまった人に
適切な言葉は「立ち止まろう」かもしれない。
立ち止まる、という言葉のあたたかさを感じた。
「立ち止まる、という言葉のあたたかさ」。
この一行に、やられました。
私には、ずしんと響いたんです。
読み手に響く文章づくりに
必要なモノって何だろうと考えた時、
この一行にあらためて気づかされました。
たくさんの言葉を知っていて
使いこなせる語い力や
行間を読ませる表現力……の
前に、物事の受け止め方や見る視点を
いかに自分らしく磨けているかだって。
一つひとつの言葉を目にした
そのままの意味で受け取るのではなく
そこに選ばれている
(あるいは自分で選んでいる)背景や理由に
想いを致して伝えられるか、
届けようとしているか。
「立ち止まる」という言葉そのものは、
とりたてて人の心を癒すものでも
やさしさが伝わるものでもないけれど
発する人の気持ちや想いが乗っかると
「あたたかい」言葉として
伝え届けることができる。
もとのお話は、無職でいることを
大切にしようという趣旨ですが
「あたたかい」という表現ひとつで
とても奥深く、
気持ちを揺らすお話に広がった気がします。
それができるようになるには
日々、自分らしいものの見方を
大切に育めるよう
感じた自分自身の気持ちに向き合えるよう
丁寧に生活することだと
改めて振り返らせていただきました。
「あたたかい」って、
高い語い力を求められるような
難しい言葉じゃありません。
日々、暮らす中で当たり前に
使っている表現です。
読み手に響く文章づくりとは、
そうした普通の日常の言葉の
選択と組み合わせから生まれるもの。
大丈夫、私たちは誰にでも
読み手に響く文章を書けますからね♪
そんな言葉と向き合う時間をお届けしています。
たまにはゆっくり、自分の中にある
言葉を引き出して磨いてみませんか?
-
 「継続」こそ最強で最短の、夢実現手段でした
メジャーリーグ162試合の実況配信が開いた夢への扉 MLB(メジャーリーグベースボール)のシーズンが始まると、
「継続」こそ最強で最短の、夢実現手段でした
メジャーリーグ162試合の実況配信が開いた夢への扉 MLB(メジャーリーグベースボール)のシーズンが始まると、
-
 ブログ記事タイトルが決まらない理由とは?
“見つけるタイトル”で読まれる記事に変える方法 「記事タイトルがどうしても決まらない…」「せっかく書いたのに、
ブログ記事タイトルが決まらない理由とは?
“見つけるタイトル”で読まれる記事に変える方法 「記事タイトルがどうしても決まらない…」「せっかく書いたのに、
-
 「起業、ちょっと気になるかも」そんなあなたへ
相談じゃなく“雑談”でいい。想いを話す、はじめの一歩 新しい年度が始まりましたね。今年も、西脇市男女共同参画セ
「起業、ちょっと気になるかも」そんなあなたへ
相談じゃなく“雑談”でいい。想いを話す、はじめの一歩 新しい年度が始まりましたね。今年も、西脇市男女共同参画セ
-
 小学5年生でもわかる文章を書くことには、ちゃんと理由がある
5年生は、まだ「○」を知らないから…… 「小学5年生にもわかる言葉で書きましょう」そんなフレーズを聞いたことが
小学5年生でもわかる文章を書くことには、ちゃんと理由がある
5年生は、まだ「○」を知らないから…… 「小学5年生にもわかる言葉で書きましょう」そんなフレーズを聞いたことが
-
 あなたの「書くのが苦手」は本当か?
“書こうとしない”発想が、伝わる言葉を生む 「ブログを書こうとしても手が止まる」「書きたい気持ちはあるのに、何
あなたの「書くのが苦手」は本当か?
“書こうとしない”発想が、伝わる言葉を生む 「ブログを書こうとしても手が止まる」「書きたい気持ちはあるのに、何