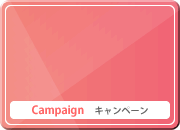- ホーム
- ブログ
ブログ
あなたの存在は、きっと誰かのお役立ちだから
2025/02/28
「プロフィールって、何を書けばいいのかわからなくて」
ブログカウンセリングや講座などで時折いただく質問です。
いわゆる自己紹介ですが、自分の何を紹介すればいいのか?
お仕事プロフィールの作成を依頼されたとき、
正解・不正解が無い中で、私が大切にしている
プロフィールづくりのベースをご紹介しようと思います。
あなたが思っている以上に、言葉には力がある
2025/02/27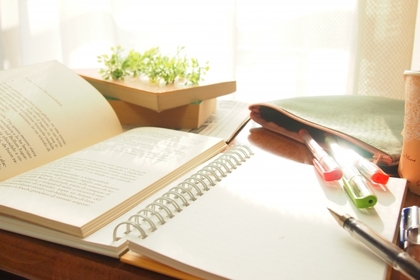
「その名前じゃ、本当に必要とする人に利用してもらえませんよね……」
会議の席で指摘が入ったのは、参加していた
ある行政団体から配られた一枚のチラシでした。
本当に届けたい人には、響かないかもしれないと
今、仕事をしていて楽しいですか?
2025/02/26
ライターという仕事を、自分の中でどう位置付けるか
ずっと迷っていた時期があります。
取材ライターなんて「自分のためでしかない仕事」。
そんな指摘を受けてから、ずっと迷いと違和感に
さいなまれる毎日でした。
取材して記事にするというライター仕事って、
「仕事とはお役立ち」という自分のポリシーに
反している仕事なのか?
自己満足でしかないのか?
手放さなくては明日はこないのか?
これまでの人生丸ごと否定を受け、
なかったことにしなくてはいけないような気がして
まわりがよく見えなくなっていたのです。
先生は本当に薬を処方しなかったのか?
2025/02/25
「うわ……先生、素敵♪」
先日、爪を傷めてしまい、ご近所のお医者様のところへ受診に行った時のこと。
中待合室に案内され、目の前にある診察室へ呼ばれるのを待っていた時
心がほっこりする出来事があったのです。
カーテン一枚で仕切られた中待合と診察室。
聞くとはなしに、聞こえてきたのは先生と、ある患者さんの会話でした。
初挑戦!インスタコラボライブ3つのポイント
2025/02/24
「インスタライブのコラボって、誰とすればいいんでしょう?」
そんな質問が届きました。
ステキなご質問、ありがとうございます♪
コラボライブに初めて挑戦してみたい!
という方のヒントになるといいなと思い、自分の経験をもとに考えてみました。
バラードを歌うように文章を紡ぎたい
2025/02/23
「あ、この車は……」
ある日の夕暮れ。
仕事を終え、車を自宅へ走らせている途中、
ライターの本棚:魂を磨く本
2025/02/22
お布施ブログ100日チャレンジの、お仲間のお一人
のブログで紹介されていた「魂を磨く本選び」のお話に心を惹かれ
魂磨きという視点で、好きな本を振り返ってみました。
阿部さんによれば、魂を磨く本の選び方にはポイントが5つ!
魂を磨く本選び5つのポイント
*すぐに役立つビジネス本、ノウハウ本はNG
*長年読み継がれているもの
*古典や歴史・文学、考えのヒントになるようなもの
*読みやすい本よりも難しい本
*仕事と関係のない本(発想力が広がるもの)
まさにぴったり当てはまる一冊を手元に置いていたんです!
あなたの言葉に力を生むもの
2025/02/21
仕事を離れて、書きたいことを書きたいように書き、
マイペースに発信する場としてnoteを利用しています。
noteでも有料記事を販売できる機能があるので、集客とか
フォロー狙いの書き手の方がフォローしてくださるケースもあるのですが
大半は、書いたことに共感してくださったり、
拙文をほめてくださったりする方とのつながりです。
先日は、母の介護時代のエッセイに共感してくださった方が
あなたの肩書きは「肩書き」じゃないかもしれない
2025/02/20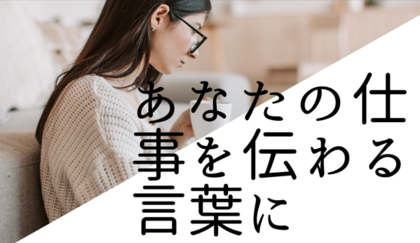
「うちはしさんって、そもそも何をしてる人?」
昔はよく尋ねられていました。
自己紹介の場では「コピーライターのうちはしです」
なんて名乗っていましたが
そもそもコピーライターなんて業界人以外、
どんな仕事なのかわからない職業です。
まったくもって自己紹介になっていなかったのです。
当時は「コピーライター」が肩書きなんだと思っていましたから。
え? それって「肩書き」じゃないの?
……そんな質問が、今あなたの頭をよぎりませんでしたか?
「文章を書き上げるのは大物作家でも難しい」
2025/02/19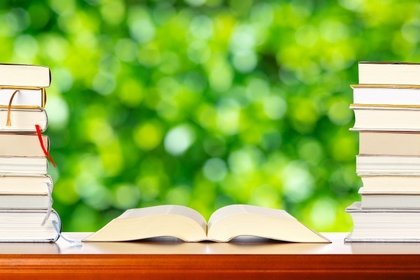
文章は「手帳」で上達する
2025/02/18
あなたも手帳、使っていますか?
新年度が始まる4月は目の前。
部署が変わったり転職したり、変化のタイミングに
手帳を見直していただけたらと思い
手帳づかいの専門家・上田直美さんにお願いして
文章は「手帳」でうまくなる!
手帳ナビゲーターに聞く「目からウロコ」の手帳術
というテーマでお話をうかがいました。
実は私も、手帳マニア。
「書く」に「話す」を加えてみたら……
2025/02/17
ずっと活字の世界で生きてきました。
今も基本的に、発信の中心はブログですが
ある時、それだけじゃだめだと気が付きました。
そこで思い切って始めたのがインスタライブです。
「動画で発信したら?」と、ずっと以前から勧められていたものの
どうしても苦手で、二の足を踏んでいました。
そんな時「インスタライブを一緒にやりません?」と声をかけていただき
「二人ならやれるかも……」と思えたので思い切って「YES!」とチャレンジ!
そして100日以上が過ぎたとき、色んな変化が起こっていました。
SEO対策と検索の大切さを思い知った記事
2025/02/15
こんな仕事をしながら、私はとってもアナログ人間です。
打合せで、Googleカレンダーを共有ツールに指定されると
使い方が覚えきれずいつもオロオロ。
LINEで「お友だちになりましょ♪」と声をかけていただくと、
どうやってアカウントを交換すればよかったか迷って
毎回しどろもどろ……。
文章を書くことは自信をもってお伝えできても、
いざSEOとか検索されやすいような仕組みとかとなると、
頭がフリーズ……。
そんなアナログ人間が、ようやっとSEO対策の必要性と楽しさを
【受講者さまご感想】ブログを書くのに疲れた人や義務で続けている人へ
2025/02/14
「好き」を仕事にできたとて、仕事は仕事ですから、
そうそう毎日毎日、楽しくて仕方ないということはありません。
時には「ホンマに好きなんか!?」って自問自答したくなるほど
いやになってしまうこともあります。
仕事が来ない
お客様に出会えない
売上が伸びない
それでも、この仕事にしがみついている自分はバカなんじゃないのかと
迷宮に入り込むことだって一度や二度じゃありませんでした。
それでも、どうにかこうにか続けてこれているのは
ご縁があったお客様の喜んでくださる様子や
届けてくださる温かいメッセージを通して
お役に立てたと思えること。
本当にありがとうございます。
今日はそんなお客様の声をご紹介いたします。
短所があなたの「得意」に変わる “魔法の言葉”
2025/02/13

自分の得意なことどころか
「好き」なものさえよくわかっていなかった私。
ちゃんと時間をかけて、自分と向き合って考えてみました。
「好き」と「得意」を引き出す12の質問に答えてみた
2025/02/12
あれは某団体さんの依頼で、文章づくり講座を開かせて
いただいたときのこと。
懇親会の席にお招きを受け、参加させていただいたのですが
そこでの雑談で、はたと考えてしまう質問をいただきました。
「これがあったら、他に何もいらないって思う食べ物ってあります?
ちなみに私はチーズなんです!」
ん? 私……何が好きなんだろ?
「フクヤマ(福山雅治)の歌で、いっちばん好きな曲ってなんですか?」
え? 多すぎて決められないけど
どれが好きかと聞かれたら……どれだっ!??????
私、自分の好きなものがわかってないのか!????????
ちょっとショックを受けました。
好きな色、好きな服、好きな場所、好きな歌、好きな数字……などなど
あなたは自分の「好き」がわかっていますか?
あなたが「好きなこと」「得意なこと」すぐ言えますか?
2025/02/11
お役立ち記事を書かねば!
ノウハウやスキルをしっかりとお伝えしなければ!
……って一生懸命に書いてた時期。
ブログや文章づくりをお伝えしている以上
私自身のブログが「アクセスが伸びなくちゃ」
「フォロワーが増えなくちゃ」「集客できなくちゃ」
と、どんどん自分を追い込んで、
理想と現実のギャップに、勝手に苦しみ勝手に悩み、
だんだんしんどくなってブログが書けなくなりました。
そんな時、ある気づきがありました。
文章を“上手に”書くために、まず決めること
2025/02/10
普段使いの言葉ほど伝わるものはない
2025/02/08
先月末のAmebaオンラインセミナーでお申し込みくださった無料相談、
皆さまとの楽しい時間が終了しました♪
ありがとうございました。
毎回、何かしら自分自身のテーマのようなものが生まれ、
勉強させていただく時間になっていますが
今回は「伝わる」が自分自身のキーワードだったかなと感じています。
苦手だった自己紹介に自信が持てた!楽しくなった!
2025/02/07
ブログやSNSを利用する楽しさのひとつに、
知らない誰かとご縁が生まれることがあるかと思います。
誰かが読んでくれた、「いいね」をくれた、メッセージやコメントが入った……
やっぱりうれしいですよね。
ましてやそれがお仕事となると、
頑張って更新している甲斐(かい)もあるし
自分と言う存在の意味を感じたり、誰かの役に立てるという喜びにも
つながりますよね。
例え何年、ブログを書き続けていても
そんな気持ちは初期のころからまったく変わりません。
最近の弊社は、そうしたつながりの入口に
「肩書きづくりワークショップ」を設置しているんです。
数字のメッセージが、あなたの力に変わる時
2025/02/04
「個性数秘学®」って耳にしたことはありますか?
唯一無二の「個性」と「人生のシナリオ」が秘められた誕生日の数字は
人生をナビゲートしてくれる秘密のコード(cord)。
その秘密のコードを読み解きながら自分の本質と向き合い
より豊かな人生を「自分の手」で「自分らしく」創造するためのもの
そんな個性数秘学®に取り組むお友だちに、ちょこっと鑑定をしていただきました。
さて、その結果は……??
「タテ」より「ヨコ」でつながればお米も事業もよく育つ
2025/02/03
「店頭からお米が消えた!」
「お米の値段が高い!」
などなど、このところお米のニュースで
世間がにぎわっています。
日本の農業を守り育て、後継者を育む施策を議論し
そろそろ本気になって政府が取り組まなくては
日本の未来がどんどん暗く、貧しいものになっていきそうで
恐ろしいなあと素人ながらに感じています。
そんな未来の日本を、明るく照らしてくれるお米づくりをはじめ
さまざまな野菜づくりなどの農業に取り組んでいらっしゃる
「農業女子」のお二人に、いろいろなお話をうかがう機会をいただきました。
選ばれなかった私の「肩書き」大公開
2025/02/02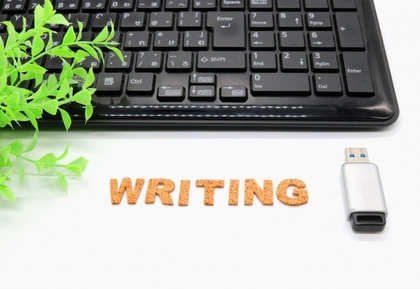
器用貧乏。
知ってます? この言葉。
私の「肩書き」だったんです(いや決して、自分でつけたんじゃない!)。
こんなこと、できますか?
あんなこと、お願いできる?
なんて声をかけていただくたび
「できるよ」「やるよ」ってお手伝いしていると
自分が何の専門家なのか、いや、そもそも
ブログや文章添削、ダメ出しされると “へこんじゃう” 方へ
2025/02/01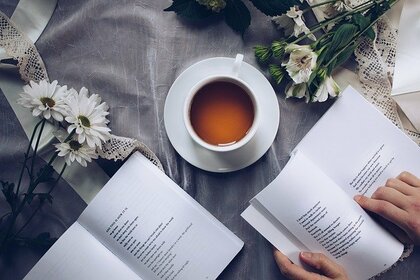
私のお仕事のひとつに「ブログの添削」があります。
「添削」なんていうと
✓ ダメ出しされる
✓ 修正される
✓ 叱られる
などなど……
「あぁ、私の文章ってやっぱりダメね」って思いこまされるサービス……
というイメージが、やっぱり強いんですよね。
amebaさんのオンラインセミナーの参加者の中にも
「ブログ添削を受けたことがない」という方のほうが
圧倒的に多かった気がします。
果たして「添削」って、本当に怖いもの???
-
 「継続」こそ最強で最短の、夢実現手段でした
メジャーリーグ162試合の実況配信が開いた夢への扉 MLB(メジャーリーグベースボール)のシーズンが始まると、
「継続」こそ最強で最短の、夢実現手段でした
メジャーリーグ162試合の実況配信が開いた夢への扉 MLB(メジャーリーグベースボール)のシーズンが始まると、
-
 ブログ記事タイトルが決まらない理由とは?
“見つけるタイトル”で読まれる記事に変える方法 「記事タイトルがどうしても決まらない…」「せっかく書いたのに、
ブログ記事タイトルが決まらない理由とは?
“見つけるタイトル”で読まれる記事に変える方法 「記事タイトルがどうしても決まらない…」「せっかく書いたのに、
-
 「起業、ちょっと気になるかも」そんなあなたへ
相談じゃなく“雑談”でいい。想いを話す、はじめの一歩 新しい年度が始まりましたね。今年も、西脇市男女共同参画セ
「起業、ちょっと気になるかも」そんなあなたへ
相談じゃなく“雑談”でいい。想いを話す、はじめの一歩 新しい年度が始まりましたね。今年も、西脇市男女共同参画セ
-
 小学5年生でもわかる文章を書くことには、ちゃんと理由がある
5年生は、まだ「○」を知らないから…… 「小学5年生にもわかる言葉で書きましょう」そんなフレーズを聞いたことが
小学5年生でもわかる文章を書くことには、ちゃんと理由がある
5年生は、まだ「○」を知らないから…… 「小学5年生にもわかる言葉で書きましょう」そんなフレーズを聞いたことが
-
 あなたの「書くのが苦手」は本当か?
“書こうとしない”発想が、伝わる言葉を生む 「ブログを書こうとしても手が止まる」「書きたい気持ちはあるのに、何
あなたの「書くのが苦手」は本当か?
“書こうとしない”発想が、伝わる言葉を生む 「ブログを書こうとしても手が止まる」「書きたい気持ちはあるのに、何